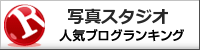7月上旬の果樹園

店裏の小さな果樹園、ぶどうの摘粒もほぼ終わり袋掛け前の状況です。
3本のぶどうの木があって品種の違いで白い袋と緑の袋を用意しています。
この景色ももう見納め、もう少しすると白と緑の袋がぶら下がった状態になります。

こちらは桃、オレンジ色の袋がかかった状態なので中がどのような状態かわかりませんが・・・・。
中に、袋をかけ忘れたところもあっておおよその状態が判ります。

この桃は無袋なので袋掛けしたものとは少し状況が違いますが、もう2週間もすれば早い物は収穫できそうです。
収穫前の今が期待だけが膨らむ一番楽しい時期だと思います。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ホタル撮影

最近、蛍病の友人からホタル撮影へのお誘いが多くあります。
大抵は出かける日の午前中に連絡が入るので、そんな日は抱えている仕事に集中し出かける時刻までには予定通り済ませるようにします。
ヒメボタルの撮影終了時刻は大抵真夜中前後、時には真夜中からスタートするような場所なども存在します。
撮影終了してから店に戻るまでおおよそ1時間、データコピーや撮影機材の片付けなどをしていると明け方近くになることもしばしばです。
ヒメボタルの撮影は毎回そんな調子です。
そして、私の場合セッティングするカメラの台数は1度に4台。
上手く撮影できれば1日の撮影で4カットの写真を作ることが出来る計算になります。
これはホタルの数によって撮影場所を変えたりすることも有るので全く予想が外れ1カットも撮れないことも有ったり、また多く飛んでいれば倍くらいのカット数の写真が出来ることも有ります。

こちらのショットは今回撮影でのお気に入りの1ショットです。
カメラの近くから遠くまでのヒメボタルが1ショットで感じよく入っていました。
もう3日もしないうちにまたお誘いが有るような気がします。
それまで集中して仕事をしておきましょう。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
雨の中ツバメを撮る

最近雨の日が続きこの日もまた雨、店の向かい側の軒先ではツバメが巣立ちの日を迎え最後の一羽の巣立ちを促しています。
余りに鳴き声が賑やかなのでカメラを持ち出し雨の中のツバメを撮影してみました。
4、5羽のツバメが巣の前を飛び交い撮影練習には丁度いいタイミングでした。

雨粒が目立つように背景が暗いところを飛ぶタイミングで撮っています。
最後の一羽が巣立つのは多分明日、撮影の好機は明日まで・・・さてお天気は?
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
西日本豪雨から6年目

先日、仕事でドローン撮影することが有ったので6年前の西日本豪雨の事を思い出し近くを流れる足守川を上空から撮影してみました。
近くの河川敷は比較的樹木が少ないですが、川下の左手奥あたりはかなり大きな木に成長しています。
僅か6年ですが・・・・手入れしないと年々状況が悪くなっていくようです。

さて、反対の川上側は?
こちらもほぼ同じような状況、上流部では太陽光発電で山肌が削られ川底には土砂が堆積、想像ですが見た目以上にひどい状態だと推察してしまいます。
雨の多いこの時期にはとても気になりますね。
足守川の両側の田んぼはすでに田植えも終わり水の入った田が広がっている状況です。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
吉備津神社 あじさい園

先日は紫陽花を撮りに吉備津神社へ。
神社のあじさい園は長い回廊の山側、ちょうど見頃を迎えている時期でした。
早朝からスマートフォンやカメラを手にした人が大勢、海外からの観光客も・・・。

雨上がりなので水滴が沢山、清々しい気持ちになります。

遊歩道に飛び出した花、見上げるように撮ってみました。

時折、また小雨が降っているようで雨の中の紫陽花印象的です。

吉備津神社で気持ちの良い時間を過ごすことが出来ました。
さて、店に戻り何時もの生活に戻ります。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
研究会の復習 その3

研究会の復習になりますが、もう1灯LEDライトをバックグラウンドに追加してみました。
スタジオ撮影ではこの追加の1灯を加えることが多いとは思いますが・・・・そちらに目が行き過ぎて・・・となる事も有り入れ方も注意する必要がありますね。
過去のブログ記事にも書いたことが有るのですが、キアロスクーロを意識すればもう少しバックグラウンドライトを右にずらす方が良いのかもしれません。
出張撮影ではその場の地明かりを手持ちの機材とバランスさせバックグラウンドライトやバックライト等の一部としてとして画面にどのように活用するかが腕の見せどころになりそうですね。
また、今回のライティングを復習する中で、過去の記事で載せたように1灯ライティングで置き換えることも出来そうです。
この辺りのことはモデルのご機嫌が良くて時間が取れる時に再度挑戦してみたいと思います。

今回の復習ではその他関連する機材の比較なども少し行ってみました。
過去にやったことがあるとは思うのですが、今ひとつ記憶がはっきりしないので、再度、再々度とその都度忘れては覚える事の繰り返しです。
また、違った発見も期待しながら・・・・。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
果樹へ農薬散布

店裏の果樹園、この日は午後から風も弱まり風向きもご近所とは反対側へ吹くようになり急遽薬剤散布をしました。
この時期は雨の日も多いので薬剤散布のタイミングが難しいです。
写真はシャインマスカットに薬剤散布しているところ、写真を見るとまだまだ摘粒するところが多く残っているようです。
ぶどうは他にセキレイという品種が1本あります。

こちらが今回使用した薬剤です。(薬剤散布は小型の動噴を使用しています)
殺虫剤と殺菌剤を混用して使用、一番奥の薬剤は展着剤でこれをほんの少し加えます。
次回の薬剤散布は果樹の状態や天気と相談ですが10日から2週間に一度を目安にしています。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。
研究会の復習 その2

前回の続き。
それでは復習の成果、学んだ事を理解し手持ちの機材と無料のモデルで再現してみました。
100%同じライティングになっているかどうか、カメラやライティング機材も全く違うしモデルや撮影場所の条件も違うので比較にならないかも知れませんが、ほぼこれで出来上がりです。
後は撮影場所の選択や背景の光などで写真の雰囲気は大きく変わってきますので、実際の出張撮影やスタジオ撮影する場合、そうした光の見極めもとても大切です。
今回の撮影、出来上がった画像を見ていると・・・もう一つ光を加えたいと思いますが如何でしょうか?
時間をつくりもう少しこの光について深めていこうと思います。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリクしてください。
研究会の復習 その1

先日、開催された岡山県写真家協会の総会と研究会。
その研究会の中で講師の方が紹介されたライティングを店のスタジオで復習。
撮影機材や物が所狭しと置かれたスタジオ(ホタル撮影やパソコンの入れ替えなどで物置状態)で仕事終了後の真夜中、無料のモデルを借り出して見てきたものを再現。

同じストロボは持ってないので当店にあるストロボを使用します。
頭の中に残っている光をフラッシュメーターを使いながら1灯づつ確認そして調整。

グリッドを付け替えながらバックライトをセッティング・・・講師の方はこのライトをキーライトと言われていましたが・・・・。

次にメインライト(このライトをなんと言われていたか・・・失念!)
研究会では布製のレフ板をボイスアクチベーションライトスタンドで使われていましたが、私は助手がいないので自立するVフラットで置き換えました。

ストロボの向きと距離、角度などVフラットから反射してくる光をメーターを使いながらセッティングして組み立て方を自分の頭にインプット。
最終調整後のライトやVフラット、モデルの位置が一番最初の写真です。
復習すると色々な事が理解でき頭にも強く残るので、昔から「予習復習は大切」と言われてきたことがこの年になって痛いほどよく解かります。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。
岡山県写真家協会総会研究会へ出席

昨日は午後から岡山市内のホテルへ県の写真家協会の総会と研究会に出席しました。
昨今の技術革新で仕事のやり方や内容が変化しているので写真業界も荒波の真っ只中といったところでしょうか。
社会問題化している少子化の影響も重なり協会員同士の話も厳しいようです。
しかし、新しい仕組みや技術も受け入れ、基礎等も学び直していかなければ新しい時代についていけません。
今回は静岡から講師に来て頂き色々と学ばせて頂きました。

魅力あふれる写真の撮り方を実技を含め学ばせて頂き、熱意あるお話の内容で私の心で消えかかっていた写真の情熱に再び火が着いたように感じました。
今回の研究会を無駄にすること無く復習を重ね、弱まり始めた写真への情熱を取り戻そうと思います。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。
桃の木の枝吊り

天気も良いので店裏の果樹園で桃の若木の枝吊り作業です。
桃の実もこれからますます大きくなり、その重さで枝が垂れ下がったり重量に耐えきれず最悪折れるので支柱を立てて針金で枝を吊り、実の重さに耐えられるようにします。

単管パイプ4m長の上下に四角いプレートを付け、この穴に被覆した少し太めの針金を通して準備を進めます。

この針金を使用、最初は一本の支柱に8本の針金を用意します。
枝に針金を止めるには枝に針金が食い込まないように古いガス管を適当な長さに切って針金に通し枝部分に当てます。

枝吊り途中の状態です。
少し枝先が持ち上がったようです。
まだまだ木が細いですが、この木で200個ほどの実を付けます。
1個250gとしても全部で50Kg程の実の重量となる計算です。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ホタルの撮影

ホタルの季節が到来したので蛍病の友人たちと夜間撮影に行ってきました。
撮影場所は岡山県の某所(蛍の撮影場所は私達のしきたりで言わないことになっています)
少し明るいうちに出かけカメラを数台セッティングしてホタルが飛ぶのを待ちます・・・・風があって多少肌寒さも感じる様な夜、果たして蛍は出るのか、飛ぶのか・・・少し不安になります。
7時・・・8時頃、1匹光り始めました。
9時頃2、3匹と数は非常に少ないですが・・・10時頃少しづつ数が増えて来ました。
11時頃心配していた空振りにはならず、少ないですが写真になるくらい飛んでいます。
11時30分撤収。
店に帰ると午前0時過ぎ・・・撮影したデータを2箇所へコピーしてこの日の夜間撮影は終了です。
時刻は既に明け方近く、ぐっすり眠れそうです。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ストロボが活躍した1日

今回出張撮影に使用したストロボ。
ゴドックスAD200とV860、各3台です。
全てにストーフェンを付けていますが、使用するモディファイヤや撮影内容によって付けたり取り外したりしています。
ストーフェンの着脱によって簡単でより多彩なストロボになり低コスト(以前は1個数百円でしたが最近は10倍近く値上がりしているようです)
また、これらの組み合わせ方によって広範囲な撮影に対応出来るので荷物も少なくなりました。
この写真の中にはありませんが封筒型の自作ストーフェンも活躍しています。
ブログの過去記事の中に有りますが、折りたたんで携帯できるのでポケットに入れ今だに時々愛用しています。
ゴドックスのストロボは専用のコマンダーでの使用とV860クリップオンストロボがコマンダーとしての機能を備えていて便利なので出番が多くなっています。
ただ、原因がハッキリしない2024年4月13日のブログ記事で書いた事が気になってはいますが・・・・。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
蛍病の友人と夜間撮影に出かける

ホタル撮影の季節が到来しました。
予想通り夜間撮影へのお誘いが蛍病の友人から入ってきました。
そして、カメラ、レンズや三脚など必要な機材をカメラバッグに詰め友人の来るのを待ちます。
撮影現場に到着し撮影機材を準備し始めると・・・・忘れ物の多いこと・・・・2回目からは忘れ物をしないようにしなければ。
上の写真はカメラのセッティングも終わりインターバル撮影を始めた後、暗闇の中友人を撮影してみました。
カメラはα6400、ISO25600、レンズはF0.95開放、1/3秒、ファインダーから人物はほぼ全く確認できませんが目測だけでなんとか写っています。

そして、新たな撮影の試みも・・・・・初回なので色々とテスト。

暗闇の中、ヒメボタルも入れてポートレイト撮影もしてみました。
写りはいい状態ではありませんが、なにか引き込まれる魅力があります。
撮影にもう少し工夫が必要です。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
修理し使い続けて半世紀

出張撮影でスタンドバッグから取り出したライトスタンド、いつものように3本足を開こうとノブに手をやると「あれっ!」感覚が違ったので目で確認。
プラスチック製のノブが真っ二つ。
幸い片割れはバッグの中に転がっていましたし、写真のような状態でも締め付け出来たので支障なく使えました。
店に戻ると早速修理。

修理はゼムクリップをバーナーで熱し割れたプラスチック部分に溶かしつけます。
手荒な方法ですが強度も出て元のように使えます。
現在使用しているものの中で私の命の次に長く使っっている機材かも知れません、かれこれ半世紀以上になると思います。
その間、何度も部品交換や修理して来たように記憶しています。

今まで色々なスタンドを使ってきましたがコメット製のこのスタンドは何故か使い勝手もよく愛着があり手放せない機材の1つです。(現在も4本全て生き延びて活躍中)
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
防蛾灯点灯

数日前から店裏の果樹園で防蛾灯を点灯しました。
桃の木に来る害虫、ヤガの活動を抑える効果があるそうな・・・夜間のみ点灯するようにしています。
黄色い光なのでよく目立ちます。
そして、この光を見るとホタル撮影の時期が到来します。

4個のLED電球を付けた手作りの防蛾灯で、蛍光灯タイプの物と取り替えて昨年から使用しています。
以前よりは少し明るくなったように感じています。
桃の管理作業の方はもう一度薬剤散布をして袋掛け作業を始めます。
さて、今年の桃の出来具合・・・7月下旬から収穫予定です。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ミニカムに替わる物

大きなホテルでパーティー、撮影依頼があり撮影機材についてあれこれ思案していました。
今までは集合写真用にミニカムストロボを使用していましたが、今回は集合写真以外にも使う場面が出てきたので写真撮影のセットを考えてみました。
ゴドックスAD200を2台、アルミフレームに取り付けカメラのホットシューにはストロボ用のコマンダーを付けています。
AD-200用のDIYブラケットでカメラに対し上下方向に振れるようにしています。(安定性の関係で写真は上下逆にして写しています)

別角度から見るとこんな感じです。(以前にも紹介したことがあるかも知れません)
AD200のフラッシュ発光部はムラが目立ちますがストーフェンを付けることで照度ムラは無くなり、変わりに中央部が明るく周りが暗くなってしまいます。
そこで2灯を写真のようにセットして周辺が暗く落ちないようにします。

本番撮影でコマンダーやカメラのセッティング中。

そして、本番撮影中。
前日に練習していた様に撮影出来、長丁場の撮影が終了しました。
この日はストロボが大活躍した1日でした。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
集合写真と個人写真の撮影に行く

軽トラに集合写真撮影機材、軽バンには個人撮影機材を積んで学校写真の撮影です。
集合写真は屋外、個人写真は屋内使用する機材と撮影場所が違うので車2台に分けて積み込みました。
天気が良いので軽トラは大活躍です。

たんぽぽの綿毛の向こうには集合写真用のヒナ段が組み上がっています。
あまりの暑さに椅子はお客様が来られるまで日陰に避難、集まってから並べます。(座面が熱くなるので)

セッティングを終えたカメラも暑さ対策で日本手拭をかけています。
余談ですが、私は日本手ぬぐいをいつも愛用しています。
汗かきなのでズボンの後ろポケットにはいつも1、2本の日本手拭を入れていますし、撮影のときなどは色々使えるのでとても重宝しています。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ぶどうの種無し処理

店裏の果樹園、ぶどうの種無し処理をする時がやってきました。
ぶどうの花が満開、この時期に1回目のジベレリン処理、そして2週間後にもう1度ジベレリン液に漬けます。
現在は、シャインマスカットとセキレイという品種をほんの少しだけ作っています。
写真の仕事で農業高校へ通うようになったので農業について少し知識を身につけようとかれこれ20年、店の裏手に畑を作り果樹や野菜を育てています。
数年前まで年に数回専門の方に見て頂き果樹について教えて頂きました。
高校でも同じ頃、同じ様な作業をするので店裏の果樹の状況を見ていれば学校での作業時期もおおよそ見当がつくのです。
農業高校には長年通っていますが、色々な作業があって未だに分からない事も多くあります。

ジベレリン処理の薬剤の調合。

薬剤は少ない量なので安価な中華製の秤を使っています。

そして、桃とぶどうの袋や殺菌殺虫剤なども仕入れて来ました。
袋掛けまでにまだまだ沢山の作業があります。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。
ツバメの宿

夜、パソコン仕事に疲れて店の外に出て深呼吸。
ふと暗い軒の下に目が行くと何やら黒いものが目につきました。
よくよく目を凝らして見ると・・・3羽のツバメがいます。
軒下LED照明用、細いコードの上(隙間)に互い違いの向きで並んで休んでいるようです。
この後も何度か見に行きましたが、やはり同じ位置で同じ姿勢、巣は向かいの家の軒下にありますが入りきれないのでしょうか。
翌朝、下には糞が数か所落ちています。

昨日、午前0時を少し回った頃、外に出て見ると左に2羽、少し離れて右に1羽がやはり同じ向きに休んでいました。
人は細い線の上で寝ることなど不可能と思いますが鳥は不思議です、どうやって寝てる間もバランスをとっているのでしょうか?
また、ゆっくり休めるものでしょうか?
余談になりますが、今回の写真はiPhoneで撮影、手持ち3秒、ところが実際の露光時間を確認すると1/5秒、このからくりは如何に。
お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。